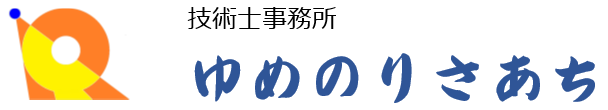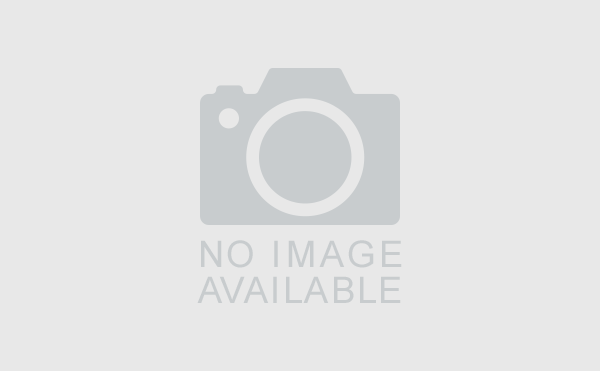ジェンダーギャップ指数2022
2022/08/14
世界経済フォーラム(WEF)は、7月13日、男女平等がどれだけ実現できているかを示す2022年度版ジェンダー・ギャップ指数を発表した。完全に平等であれば“1”、できていなければ“0”となる。日本の指数は0.650で、調査対象141か国中116位。上位国は、アイスランド、フィンランド、ノルウェーであった。
指数は4つの分野(経済への参加と機会、学歴、健康と生存、政治的権限の付与)で評価される。経済への参加と機会の分野については、日本は121位。この分野の1位はラオス人民民主共和国、その他アフリカの国などが上位にランキングされているのを見ると、先進国だから上位ということでもないようだ。学歴の分野では、日本は同位の1位21か国のうちのひとつ。健康と生存の分野では、63位。平均寿命が長いからといって上位にはならない。政治的権限の付与の分野では、139位。ほぼ最下位となっている。調査対象国全体でもこの分野の平等指数は低いが、その中でも日本は特に低い。
経済への参加と機会の分野での評価を見て考えさせられるのは、指数が1に近くても必ずしも良いとは言えないのではないかということ。望ましい男女平等はどうあるべきか。子供を育てるのは人間として大切な行為であり、母親にしかできないことがある。母親は特別な存在である。すべてを男女平等でということは不可能である。子供を育てることを中心に考えて、女性が子育てに専念したいと思えばその選択ができ、子供を育てながら働きたいと思えばその選択ができる。育休が終われば差別なく業務に復帰できる。それが叶うように配偶者、社会が支援する社会。この点で日本は諸外国よりも遅れているのであろう。政治的権限の付与の分野については、日本では女性議員数や閣僚数が少ないという。
ジェンダー・ギャップは社会の風土、慣習が大きく影響している。ただ唱えているだけで変わるものではない。あるべき姿を目指すためには、先ずは半ば強制的に数値目標を規則、ルールに設定して運用していくことであろう。はじめは違和感、抵抗もあるであろうが、繰り返し行動することが習慣となり、やがて馴染んでいくのを待つことである。