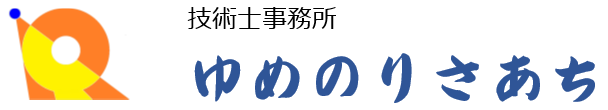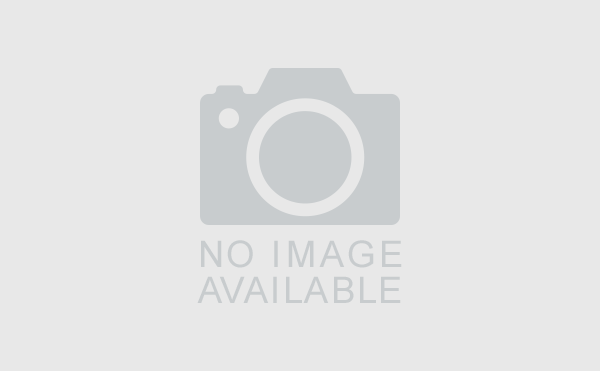日本は何をめざすのか
2022/07/08
経済状況を計る指標が株価だとすれば、日経平均株価が4万円に迫った1989年が最高潮の年であった。以降、バブルが弾け、経済は低迷し、失われた10年、失われた20年と言われ、既に失われた30年を通り過ぎてしまった。2021年の日経平均株価が1989年末の8割以下である一方で、世界の主要国の株価は何倍もの伸びを示しているという。
GDPで見てみれば、日本のGDPが世界のGDPに占める比率は1994年にピーク値を示して約18%であった。最近では6%を下回っている。世界経済における日本の存在感も小さくなってしまった。世間は日本経済の凋落を嘆いている。
しかし、バブルと言われた時代はどうであったか。家は買えない、生活もできない、狂乱物価だと言って経済の猛烈な熱を批判していた。その反省のもとに、金融政策、経済政策がとられ、民間の活動を合わせた結果として、物価を下げ、賃金を下げてきたのではないだろうか。今では、多くの主要先進国よりも安くハンバーガーが食べられるらしい。これはバブル当時に思い描いていた理想の日常ではなかったのか。
失われた30年を過ぎて、追い求めるべきは、本当にインフレ率2%以上、GDP拡大なのだろうか。この間の日本の一人当たりGDPは、世界の主要国の伸びには見劣りするものの増えてきた。少子高齢化、人口減少の中においても緩やかに増加していることは評価されるべきものではないのか。環境問題が際限のない生産や消費に疑問を呈している現代において、高い経済成長よりも、穏やかな成長や停滞はむしろ望ましい形のように思える。
株価やGDPよりも取り組むべき指標があるのではないか。2021年の国連世界幸福度ランキングにおいて、日本は56位である。また、従業員エンゲージメント、即ち、士気・熱意のある従業員の割合は、アメリカ・カナダが34%、世界では20%であるのに対して日本は5%だという。これこそ日本の問題点であり、取り組むべき指標なのではないか。人々の幸福度の向上、職場においては従業員のエンゲージメントの向上を軸に据えて活動していくことで、本質的に豊かで充実した生活、社会が実現できるものと期待したい。