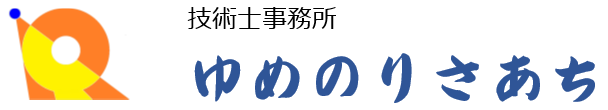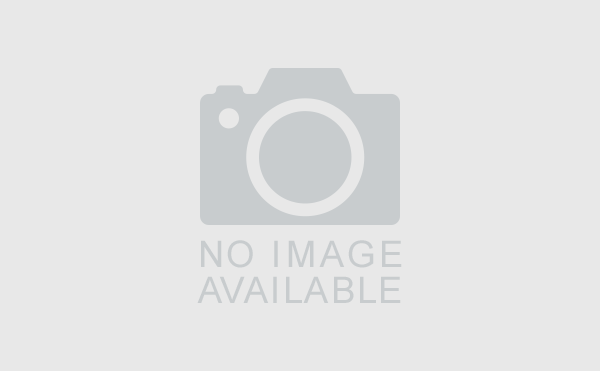次世代半導体
2022/08/02
2022年7月29日、ワシントンで日米の外務・経済閣僚協議「経済版2プラス2」の初会合が開催された。米中の対立が懸念される状況において、日本とアメリカが、外交・安全保障と経済の面から協力して中国に対抗していこうとする仕組みである。
その中で注目されるのが、回路幅が2ナノ相当の次世代半導体を共同研究しようとするものである。日本は年末までに新たな研究機関として次世代半導体製造技術開発センターを立ち上げ、産業技術総合研究所、理化学研究所、東京大学などと協力していく。そして、米国国立半導体技術センター(NSTC)と協力していく。
かつて1980年代には、世界の半導体メモリDRAMのシェア80%を日本製が占めていた。しかし、その後日本の半導体産業は凋落した。技術は最高との思い込みに浸りつつ、ニーズに合った品質と価格のバランスを取ることができずに、韓国、台湾メーカーの後塵を拝することになった。ついには日本のDRAMメーカーはなくなった。2019年の世界の半導体産業売上額における日本のシェアは10%。そして現在、半導体の回路幅が10ナノメートル未満の先端品の生産能力の90%は台湾にあるという。
今後に向けてアメリカは、半導体の生産・研究に7兆円の補助金を用意することになった。日本でも、10年で1兆円の研究開発費を用意する案があるようだ。ただ、補助金を出せば上手くいくというものではない。日本の半導体産業が下降線を辿る時代、多額の予算をつけて数多くの研究開発国家プロジェクトが作られた。しかし、産業復活につながる成果を上げることはなかった。
これから作られる次世代半導体製造技術開発センターは、2025年に量産態勢の整備をめざすという。かつての失敗を繰り返すことは許されない。資金を出す国、研究する研究所や大学、量産技術を担うメーカーそれぞれが、同じ大目標を見据えつつ、コミュニケーションを密にして、自分事としてプロジェクトに取り組むことが成功の必要条件である。先ずは2025年の成果に注目したい。そして、その後の2030年ごろの日本の半導体産業がどうなっているか。見守っていきたい。