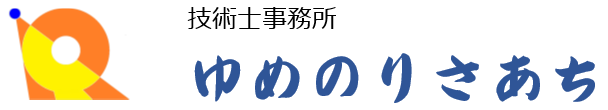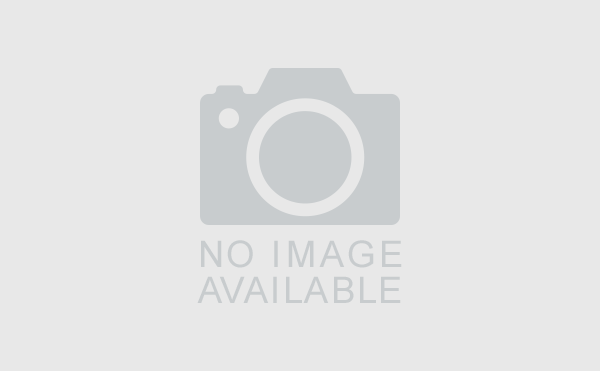賃上げ
長らく上がらなかった日本の賃金が、2023年の今年、大幅に上がった。OECDの資料によれば1991年から2020年の30年間でのG7各国との賃金推移を比べると、名目賃金は、米国2.79倍、英国2.66倍の上昇に対し、日本は1.11倍。実質賃金は、米国1.47倍、英国1.44倍に対し、日本は1.03倍で停滞してきた。名目賃金の伸びを1年に直せば0.35%だ。それが今年は、民間主要企業の賃上げ率は3.60%だった。
しかし、現実的には賃金が上がったと喜んではいられない。厚生労働省が12月8日に発表した10月の毎月勤労統計調査によると、一人あたりの賃金は実質で前年同月比2.3%減った。マイナスは19カ月連続だ。賃金が上がったと言っても、物価はそれ以上に上がっているということだ。庶民の生活は依然として苦しいまま、いや、さらに苦しい方向に進んでいることになる。
あるコンサルティング会社が、連結報酬などが開示されている時価総額上位100社を対象に調べた。日本の社長報酬は2022年度実績が2億2000万円で2021年度から2割増であったとのこと。庶民からすれば、驚くべき金額であり、増加率である。閉塞する経済の中で社長報酬だけが上がっていていいのかという思いは禁じ得ない。
優れた経営者を確保するためには外国並みの高い報酬が必章だとの議論がある。どれほど優先すべき事項なのだろうか。従業員の賃上げ率を外国よりも低く抑えながら、経営者自らは外国並みにすることを名目に報酬を上げてはいまいか。賃金を上げよとの世論の高まりの中で今年の賃金は上がったが、これまでも経営者が上げようと思えば上げることができたのではないのか。
若い世代は子供を育てるために共働きをして、将来を心配しつつ経費を切り詰めて生活している。経営者は従業員の賃金を抑え、将来に向けて成すべき投資を怠り内部留保を膨らませ、経営者報酬は上げてきたように見える。経済全体を旨く回していくためにお金は正しく使われてきたのだろうか。
30年にわたり経済が停滞するこの時代を、50年後、100年後の脚本家はどう描くのだろう。経営者たちは庶民と苦労を共にするリーダーなのか、それとも悪代官なのか。
以上