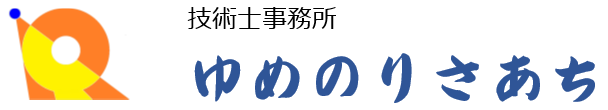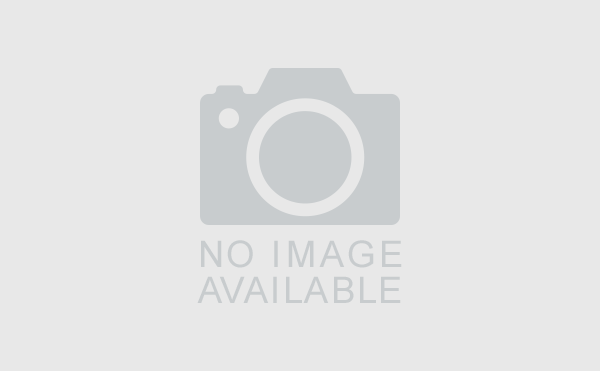ホンダと日産の経営統合
ホンダと日産自動車が経営統合に向けて協議を始めるらしい。持ち株会社を2026年8月に設立して、両社が傘下に入る。三菱自動車が加わるかは来年の1月に決めるとのことだ。参加しないという選択肢はないのではないか。この3社が統合すると、世界販売台数でトヨタグループ、フォルクスワーゲングループに次ぐ世界3位になるという。
自動車産業ではEV電気自動車への移行、自動運転への進化など、100年に1度の変革期にあると言われている。この変化の中で、テスラや中国の新興自動車メーカーが台頭してきた。既にEV化で後れを取っていると言われる日本メーカーが安閑としていられる状況ではない。ホンダと日産が経営統合するとのニュースは驚きであるが、大きな決断をしたと前向きに捉えたい。
自分が子供の頃、アフリカのサファリ・ラリーで日産ブルーバードが優勝した。土煙を上げながらアフリカの大地を疾走する日本車を子供ながらに誇らしく思った。1970年代、大気汚染を規制する米国のマスキー法に対して、GM、フォード、クライスラーなどビッグ3が達成は不可能であると反対する中、ホンダがCVCCエンジンを開発して規制をクリアした。日本車の評判が高まり、日本の自動車産業は盛隆を極めてきた。それが今、100年に1度の曲がり角だ。
今後の自動車には電動化、AI、ソフトウエアなどの技術が問われる。ホンダと日産は、台車やソフトウエアの共通化を目指すという。企業が統合する時、どちら由来の技術を採用するかで揉めがちだ。かつて日本の半導体産業が凋落する中で、日立とNECの半導体部門が統合してエルピーダメモリが設立された。期待されていたが、結局破綻した。両社の技術覇権の争いによる事業の非効率が原因と言われている。
自動車産業は日本経済の屋台骨である。ホンダと日産が不毛な内部争いにより衰退するようなことになれば、日本経済への負の影響は甚大だ。ホンダ、日産、三菱の全役員、社員には、置かれた状況に危機感を持ち、冷静に、そして謙虚であってほしいものだ。お互いの風通しが良く、目指すところを1つにしてまとまり、全員がモチベーション高く働ける会社になることを祈る。
以上