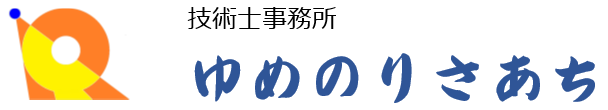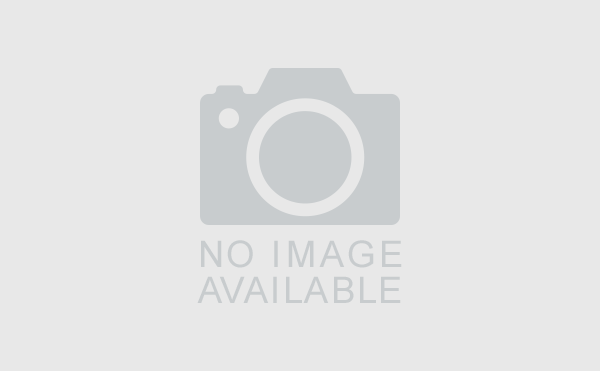八潮市道路陥没
八潮市の道路が陥没してトラックが転落した。運転手が行方不明になってから1か月になろうとしているが、未だに行方不明のままだ。事件発生直後には呼びかけに応答していたというから痛ましい。
道路陥没の原因は、下水管の老朽化に伴う腐食だ。腐食した部分から周囲の土砂が流失して道路の下に大きな空洞を作っていた。運転手の救出を妨げたのは、新たな陥没の広がりと、流れ込み続ける汚水。汚水の流量を下げるために、埼玉県の12市町で水道使用制限が呼びかけられ、生活に大きな不便を強いられることになった。
海外の出来事として、道路の穴に車や人が落ちる映像がテレビで紹介されることがあった。今回の陥没事故も海外の話かと思った。しかしこれは日本で起きたことだ。しかもこれほど大規模な崩落は見たことがない。
日本の下水道に起因した道路陥没は、2022年度で約2600件も発生していたという。標準的な耐用年数は50年で、これを超えた管路は22年度末で約7%。10年後には約19%、その後急速に増えていくらしい。八潮市で破損した下水管は敷設後42年とのことなので、50年未満だからと安心はできない。下水で発生する硫化水素が腐食を早める。
水道、下水道は自治体によって料金収入で運営されている。人口減少や、節水家電の普及により、多くの自治体では赤字運営で、施設の維持更新に充分な予算が回らないという。更には技術者の減少による対応力の限界、技術の継承にも問題があるようだ。
普段あたり前のこととして水道を使い、水を流している。八潮市の事故があって、あらためて普段見えない道路の下に水道がとおり、下水道がとおり、我々の生活を支えてくれていることを認識する。全国の下水管の総延長は約49万キロメートルで、これは地球のほぼ12周分に相当する。これだけの下水管を作ったことは凄いことだ。これからはこれを適切に維持管理していかなければならない。さもなければ、普段の生活が文字通り足元からすくわれる。
家の近所の道路で水道管の耐震化工事が続いている。道路が片側通行となり不便を感じるが、必要かつ重要な工事だと理解しなければいけない。上水道も下水道も重要なインフラであり、地震にも、老朽化にも備えていかなければならない。
以上