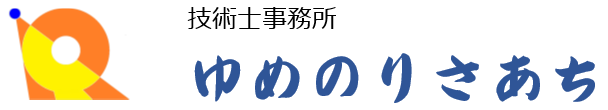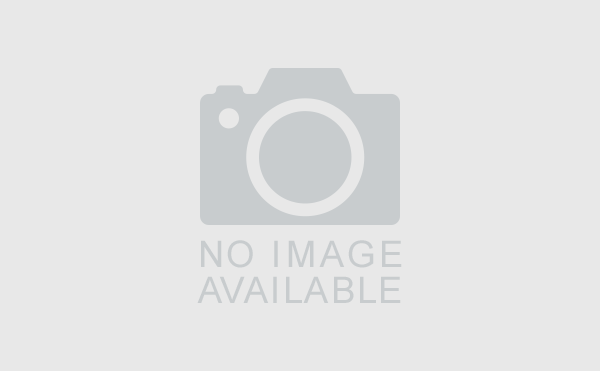ノーベル賞
10月に入ると始まるノーベル賞ウィーク。期待交じりに迎えた初日の10月6日、いきなり生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文さんの受賞が発表された。日本の夕方にうれしいニュースがいっせいに流れた。そしてなんと8日には、京都大学特別教授の北川進氏が化学賞を受賞。日本の研究力が低下していると危惧される中で、同年ダブル受賞は2015年以来10年ぶりの快挙とのことで報道は沸き立った。
坂口さんの受賞は、免疫反応を制御する「制御性T細胞」を発見し、その働きを解明したことが評価された。この発見は、自己免疫疾患やがん治療に新たな可能性を開き、アレルギーや臓器移植拒絶反応の克服にも貢献すると期待されている。
北川さんの受賞は、金属と有機物を組み合わせることで、内部にナノサイズの空間が多数ある「多孔性材料」を開発し、その空間に気体などを吸蔵・放出できることを実証したことによるもの。この多孔性材料は、有害物質の吸着やCO2回収など地球環境問題への応用が期待されている。
ノーベル賞受賞と聞けば、その輝かしさに目が奪われるのだが、お二人ともに、すべてが順調だったわけではないとのことだ。画期的な研究だからこそであろう、初めの頃は研究成果を信じてもらえず、論文掲載を断られる屈辱も味わってきたらしい。それでも地道に研究を続けてきた。
科学論文数で日本は1990年代後半に米国に次ぐ世界2位だったものが、2025年には5位に後退している。引用回数が上位10%の注目論文数にいたっては13位だという。博士号取得者も増えていないらしい。日本の研究力は凋落していくのだろうか。
おもむきは大分変るが、今年のイグノーベル賞を日本の「シマウシ」の研究が受賞した。なんと日本人の受賞は19年連続だそうだ。イグノーベル賞の趣旨は、「人々を笑わせ、そして考えさせる研究」を称賛し、科学や技術、医学などへの人々の関心を高めることとある。科学の多様性や創造性を讃える賞だ。日本にはまだまだ優れた研究への種火が残っていると信じたい。意欲ある若者が研究に興味を持つようになり、そして生活に困ることなく伸び伸びと研究できる環境づくりを強力に進めてほしい。そして研究力の炎を燃え上がらせてほしい。
以上