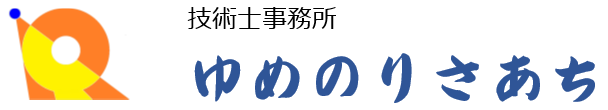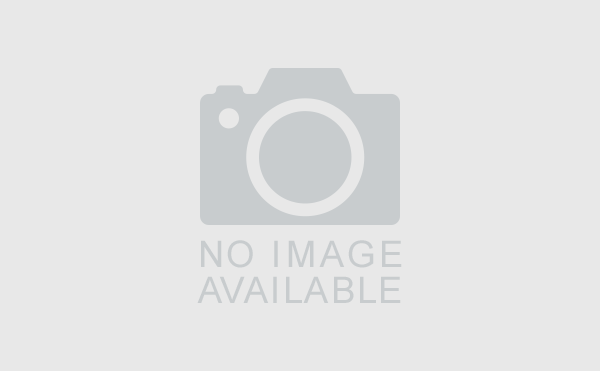三菱スペースジェット
2023年2月7日、三菱重工は国産ジェット旅客機事業から撤退することを発表した。2020年の秋に開発凍結の発表があったものの、コロナ禍が過ぎ去り、旅行者が戻るようになれば再開されるものと大いに期待していた。残念な結末となった。事業撤退のニュースがさほど大きく取り上げられることもなかったことからすると、開発凍結の時点で、事業撤退は既に規定路線となっていたのであろう。
「MRJ」という名称でジェット旅客機の開発が始まったのは2008年。初飛行に成功したのは2015年。YS11以来50年ぶりの国産旅客機ということで、国民は喝采した。自分も繰り返し繰り返し、何度初飛行の映像に目を凝らしたことか。
開発計画頓挫の原因はどこにあったのだろう。第一に気にかかるのがビジネス環境の問題。新たな分野に進出することは常に難しいが、特に航空機産業はアメリカ、ヨーロッパががっちりと握り参入障壁が高い。三菱は事業参入にあたりボーイングとコンサルティング契約を結んだが、ボーイングに本気でサポートするつもりがあったのだろうか。ボーイングにしてみれば、小型機分野とは言え、競争相手を育てることにもなりかねない。どこまでコンサルティングが機能したのだろう。
第二に、三菱内部の組織運営の問題。思いだされるのが客船事業の失敗だ。新聞、テレビの報道から振り返ると、どちらも似たような状況で失敗したように見える。部分部分の技術はあっても、それを規定の品質、要求仕様にまとめ上げる力が不足していた。行き詰ると、知見ある外国人を雇ったが、外国人との役割分担、組織化が旨くいかなかったのではないか。
誇り高き技術者は自分たちでできると言うであろう。日本人社員と、外国人専門家の協力体制を作ることができなかった。日本人社員の心情を知る日本人社長であればある程、仕切るのは難しかったと推測する。
三菱重工の人々は誇り高き人々であるに違いない。三菱重工の存在は、国民の誇りでもある。しかし、そこに落とし穴はないか。誇りは頑張りにつながるが、面子にこだわれば驕りにもつながる。それは失われた30年を過ごす我々一人ひとりが振り返るべきことでもあるように思う。
何かと縮み志向の今の日本において、大きなプロジェクトへの挑戦をやめてはいけない。三菱重工が抱えるビッグプロジェクト、H-Ⅲロケット、次世代原子炉、などなど。失敗を乗り越えて成功を祈る。国民の期待がかかっている。
以上