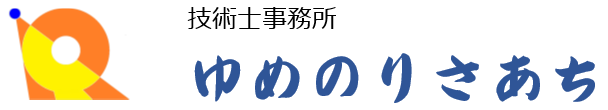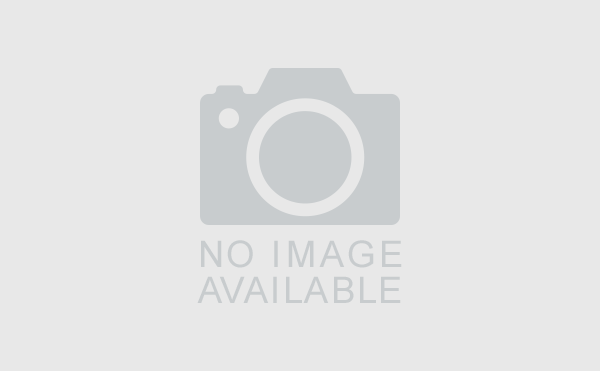学習到達度調査
経済協力開発機構(OECD)は昨年の12月に、世界81カ国・地域の15歳69万人を対象に2022年に実施した学習到達度調査(PISA)の結果を公表した。日本の順位は「読解力」が前回2018年調査時の15位から3位に、「科学的リテラシー」も5位から2位に、「数学的リテラシー」は6位から5位に上がった。
コロナの影響によりOECD各国で3か月以上の休校が多かった中で、日本の休校期間が短かったことが、日本の順位を上げたとの分析である。これは、外部要因による結果だということかもしれないが、勉強すれば順位が上がるということを示しているとも捉えられる。PISAの順位は調査年ごとの変動も大きいようで、過度に結果に拘ることはできないが、順位が上がったことは素直に喜びたい。現場の先生たちの創意工夫、試行錯誤の努力の結果であろう。
子供たちの教育を支える先生たちの労働環境は過酷だ。OECDの国際教員指導環境調査(TALIS)2018の報告によれば、日本の小中学校教員の1週間当たりの仕事時間は最長。中学校の課外活動(スポーツ・文化活動)の指導時間が特に長い。その一方、日本の小中学校教員が職能開発活動に使った時間は、参加国中で最短だという。
文部科学省の学校教員統計調査によれば、2021年度に精神疾患を理由に離職した公立小中高校の教員が953人に上り、前回の2018年度より171人増加した。
この10年来、公立学校教員採用選考試験への全体の受験者数も競争率(採用倍率)も減少し続けている。令和3年度の実施では、受験者総数は、126,390人で、前年度に比較して7,877人減少、全体の競争率は、3.7倍で前年度の3.8倍から減少した。
学校教員の過酷な労働環境を改善しなければ、質の良い教育の継続は困難である。教員の過負荷を解消しなければならない。課外活動の指導や事務作業などは外部の専門家や支援者に任せればいい。定年を過ぎた人たちの活用だってあるのではないか。生徒たちが、教師以外の大人たちと接することも立派な教育になると思う。
教員になろうと志ある人が増え、プロの教員に育っていくことがこの国の土台になる。優秀な先生に導かれ、生徒たちがいろいろなことへの驚きや、憧れを感じながら、自ら目を輝かせて学ぶようになるのが目指すべき理想の姿だと思う。
以上