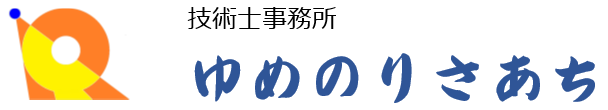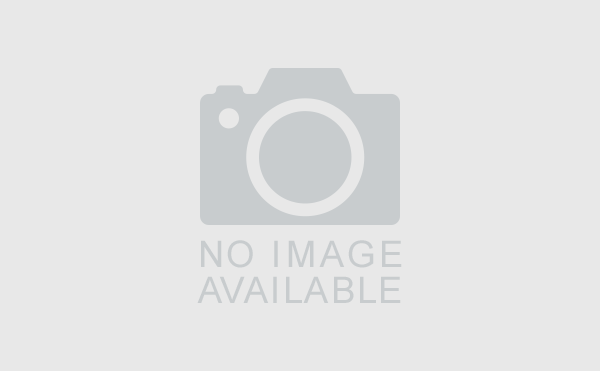国産旅客機再挑戦
経済産業省が3月27日、2035年ごろをめどに官民で次世代国産旅客機を開発する案を発表した。脱炭素の将来需要を見据えて水素エンジン旅客機の開発を想定する。今後10年で官民合わせて5兆円を投資するという。
三菱重工の国産ジェット旅客機(MSJ)事業からの撤退発表から1年での旅客機事業再挑戦の狼煙である。MSJ失敗といえども、それまでの経験、ノウハウの蓄積があったはずである。また、多くの関連企業も投資をし、技を磨いていたはずである。それらを全て無にしてしまわないために、時間を空けずに旅客機事業に再挑戦することは理解できる。は果たしてこれが名誉挽回となるか、深手を負うことになるのか。
新たな挑戦が成功するためには何が必要か。
技術力。MSJの時は、作るのも、審査するのも、検査の方法も手探りであった。やはりゼロから世界一級の旅客機を作るのはハードルが高かった。経験を踏まえて更なる進化を期待したい。
プロジェクト遂行力。MSJの反省に立って、今度は複数社で開発し、自動車メーカーなどとも連携するとのことだ。悪いことではないが、メーカーを数多く集めたからといって旨く行くものでもない。多くの利害関係者をまとめる協力体制、強力なリーダーシップが求められる。
マーケット。MSJは座席数70席、90席の国内線航空機をターゲットとした。それは妥当であろう。販売先はどうであろうか。販売数確保の期待を込めて、インドとの連携という選択肢はないのか。国土は広く、人口は世界一、宇宙技術も進んでいる。
MRJでの投資額が、経産省500億円、三菱重工が1兆円であったことを考えると、今後10年で5兆円の投資は、かなり意欲的である。しかし、それに対する企業、世間の反応は冷めているようだ。計画は動き出すのであろうか。
プロジェクトの成否を決めるのはやはり人である。経産省が、予算を取ったのだからこれでやれという態度では旨くいかない。参加企業側でも、やらされ感漂う対応では旨くいくはずがない。新たな航空機産業を作るという目標を見据えて、政府、大企業、それを支える中小の企業が一丸となって成功させることを期待したい。10年後である。
以上