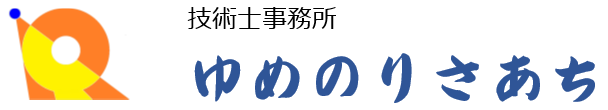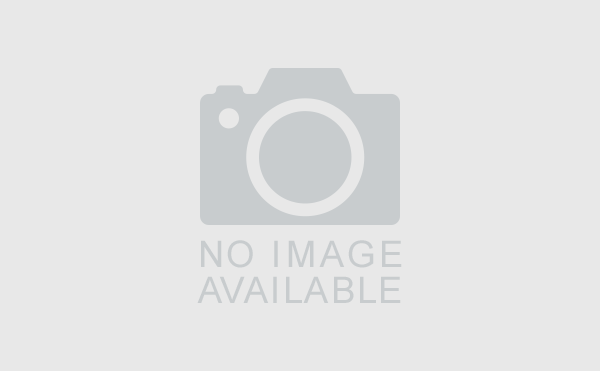電話と特殊詐欺
「電話には出ないようにしましょう」。特殊詐欺への注意を促すチラシには、そう書かれている。今や、電話に出ないことは常識だ。
お年寄りが特殊詐欺に騙されて大金を盗まれたというニュースは日常茶飯事である。還付金や補助金をかたった新たな詐欺が次々に出てくる。特殊詐欺グループの手口は巧妙になり、組織化、グローバル化している。
むかしの記憶をたどれば、1980年代には電話が掛かってきたら先ず自分から名乗っていたものだ。しかもこちらの誠意を示すがごとく機嫌よく、はっきりと名乗る。それがマナーであり、常識であった。
その後、アメリカで生活する機会があった。既に現地で生活していた日本人に言われたのは、電話が掛かって来ても自分から名乗ってはいけないというものであった。何だかぞんざいな感じがして戸惑った記憶がある。いろいろと宣伝の電話が掛かってくるのも日常で、電話文化の違いを感じた。今にして思えば、当時の日本はまだ古き良き時代を残していた。そして日本も変わっていった。
テレビの特殊詐欺のニュースはご丁寧にもどのような手口でお年寄りが騙されたのか、いくらの被害を受けたのかが伝えられる。テレビ局は何を思って報道しているのだろう。高額の被害額は新たな模倣犯を刺激しているのではないか。だましの手口はそのまま新たな詐欺のマニュアルになってはいまいか。犯罪の抑止になるような、詐欺グループの逮捕、刑罰に関するニュースはほとんど見ることがない。
電話会社は特殊詐欺防止につながる研究開発、技術開発をしているのだろうか。通信には「通信の秘密」というのがある。「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と憲法に定められており、通信関係の法律でも「通信の秘密」が定められている。電話会社が法律を遵守することは当然であるが、「通信の秘密」を口実にして特殊詐欺の対策に手をこまねいていることはないのか。
電話会社は危機感を持って、そして社会全体で特殊詐欺の防止に取り組んでいかなければ、電話は災いの窓口、使えない遺物になってしまう。
以上