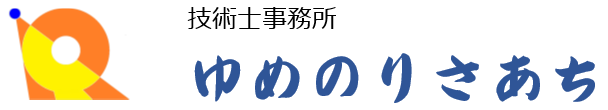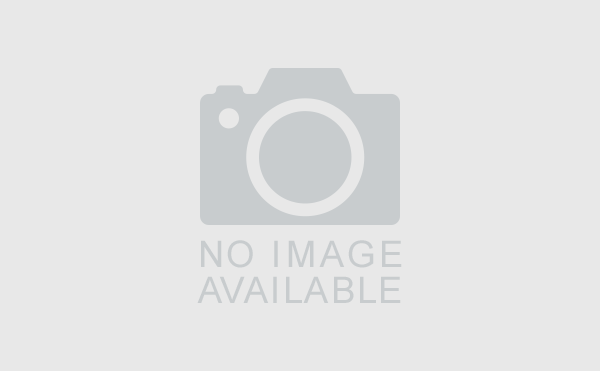ある日多摩川の土手にて
雨上がりの午後、多摩川の土手を散歩した。アスファルトの上に赤ちゃんカタツムリが、あちらにもこちらにも、何匹も、いや何十匹も這っていた。毎年この時季になると這い出てくる。直径5ミリ程の黄緑色の半分透けるよう殻を背負って這っている。どこへ行きたいのだろう。誰かに踏みつけられる前に、早く安全な草むらへ行くんだよ。
また別の日の午後、多摩川の土手を散歩していた。10メートル程先に久しぶりにヘビを見た。あれは青大将に違いない。1メーターはあった。土手の右側の草むらから出てきて土手のアスファルトの上を体をくねらせながらゆっくりと這っていた。5メートル程まで近づいたらヘビも気がついたのか、数秒ほど動きを止めて、もと来た草むらへ慌てて戻っていった。そちらの方は住宅街の方だけど。どこへ行ったのかな。
河川敷には木も生えて草むらが一面に広がっている。その草むらを見ていて気になることがある。草むら全面がつる植物の葉っぱで覆いつくされているのである。葛だ。
ネットの情報によれば、繁殖力が高く、除草剤に強く、根絶は困難とある。1876年のフィラデルフィア万国博覧会に日本から運ばれて飼料作物および庭園装飾用として展示された。それをきっかけにアメリカでは東屋やポーチの飾りとして使われるようになったらしいが、その後、繁茂力の高さから侵略的外来種に指定されて駆除が続けられているとのことだ。海外では世界の侵略的外来種ワースト100に指定されている。
日本では古くから食用や薬用に用いられてきた。根に含まれるデンプンをとり、葛切りや葛餅、葛菓子の材料になる。若芽も食べられるらしい。根を乾燥させた生薬は葛根。風邪の初期症状に用いられる葛根湯の主薬である。
夏から秋にかけて、紫の房状の花をつける。花は万葉の昔から秋の七草の一つに数えられている。絵画や意匠の題材としても扱われ、葉を意匠的に図案化した家紋が数多く存在するそうだ。
かつて人々は葛を利用し、野山に広がる葛の手入れもしていた。しかし今は放置されていて、威圧的に繁茂する雑草にしか見られない。葛の長所を活かすことができていない。でもそれは、葛にとっては幸せだ。
以上