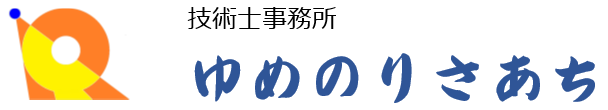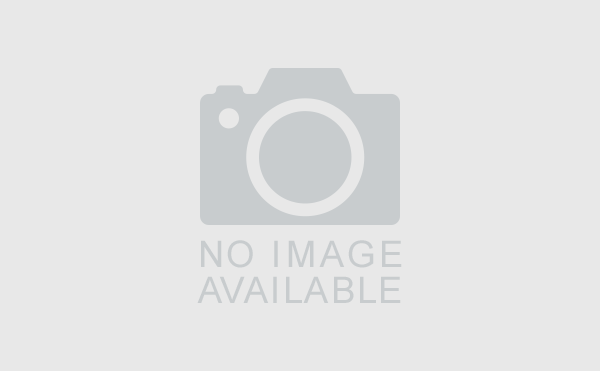日野自動車の不正問題
2022/08/16
日野自動車が、排出ガス性能と燃費性能を偽って認証を取得した不正問題。これに関して、外部有識者で構成される特別調査委員会の調査報告書が8月2日に公表された。報告書は、問題の真因として、①みんなでクルマをつくっていないこと、②世の中の変化に取り残されていること、③業務をマネジメントする仕組みが軽視されていたこと、を挙げた。分かりやすく言えば、セクショナリズムが強く、組織がタコ壺化し、全体最適ができなかった。自由闊達な議論をしていなかった。現場と経営陣の認識に断絶があった。「上に物を言えない」、「できないと言えない」風通しの悪い組織となっていた。開発プロセスに対するチェック機能が不十分であった。パワートレイン実験部が開発業務と認証業務の双方を担当していた。規定やマニュアル類の整備が十分でなかった。
日野自動車では、少なくとも2003年から不正を重ねていたことが明らかとなり。不正対象車は56万台になる。そして、販売台数の5割以上の車が出荷停止となっている。油圧ショベルやクレーンなどに日野自動車からエンジンを調達してきた企業、日野自動車に部品を納めてきた関連企業にも影響が広がっている。日野自動車の今後はかなり深刻なものと考えざるを得ない。
日野自動車に対しては、数々の厳しい批判が投げかけられるであろう。しかし、これを日野自動車だけの問題とすることはできない。事実、だれでも知っているような大企業をはじめ、これまでに発覚した不正問題は枚挙にいとまがない。
不正問題は、日本企業の技術力が低下し競争力がなくなってきたことによる苦し紛れの状況を表しているのかもしれない。不正は絶対にしないと、誰が言えようか。その日の体調、置かれた状況により、人間の判断は揺れる。疑問を持つこともなく目の前の仕事にひたすら打ち込む、自分の意見を主張しない。そういう日本人気質の負の側面の表れかもしれない。不正は起こり得る、間違いは起こり得るということを前提にシステムを作り、絶えず見直しをかけるマネジメントが必要である。