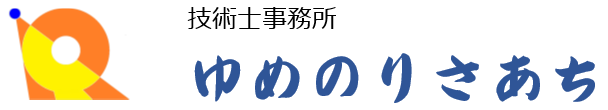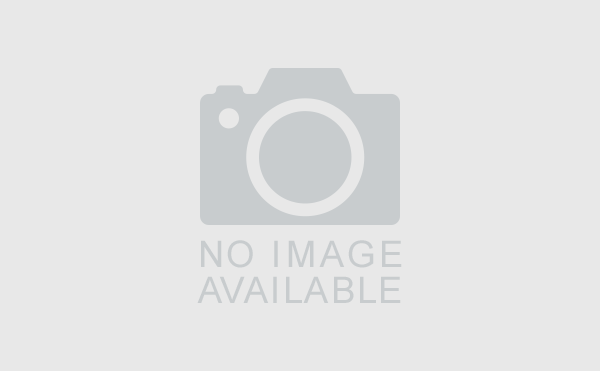日本の生産性
2022/09/30
日本の生産性は低いと言われている。OECDのデータによれば、2020年の一人当たり労働生産性は38か国中28位、時間当たり労働生産性はOECD加盟38か国中23位となっている。しかし、日々の生活の中で日本人の働きぶりを見ていて、生産性が低いという評価には納得し難いものがある。スーパーマーケットのレジにしても、郵便局の窓口にしても、飲食店のサービスにしても、素早く、正確で、丁寧だ。生産性が高いと評価される国々と比べて劣っているとは思えない。
日常の生活の中で感覚的に捉える生産性と、指標として算出される生産性とには違いがあるのであろう。一人当たり労働生産性とは、一定期間の国内の総付加価値を労働者数で割ったものであり、時間当たり労働生産性は、一定期間の国内の総付加価値を労働者の総労働時間で割ったものと定義される。
定義の分子にある総付加価値が小さければ生産性は低くなる。生産性を上げるためには付加価値を大きくする必要があるが、魅力ある製品やサービスが生み出せていない、値付けが低すぎる、値上げしたくてもできない、という状況かもしれない。定義の分子の労働者数が多ければ、一人当たり生産性は低くなる。総労働時間が大きければ時間当たり生産性は低くなる。
消費者から見れば、安く製品やサービスを買えるということは悪いことではないし、多くの人で仕事を分け合うことで失業率が低く抑えられているのであれば、良い社会なのかもしれない。だからと言って、今のままで良いということでもない。常により良くすることを考えていかなければならない。
日本の現状において生産性を向上させるために考えるべきは、より早く作業するということではなく、いかに無駄を省くかということであると思う。働き方改革として労働時間の短縮が唱えられる中で、強制的な退社時間の設定が行われたりするが、習慣的にやってきた無駄な会議、資料作成の廃止は進んでいるであろうか。
すばやい意志決定というのも日本の課題であろう。日本の会社では物事を決めるのに時間がかかると言われる。稟議書には多くの人がハンコを押さなければならない。会議には多くの人が集められる。多くの人のコンセンサスが得られるというメリットがあり、バランスの問題であろうが、バランスの位置がずれてはいまいか。
問題の根本は、だれもリスクを取ろうとしない、だれも責任を取る覚悟を持たない、責任の所在が不明な無責任社会ということではないのか。一人ひとりが主体性を持つ心がけで働くこと、よく考え、責任も負って行動することができた時、職場は活性化され生産性が高まっていくのではないだろうか。